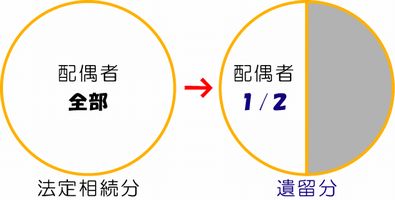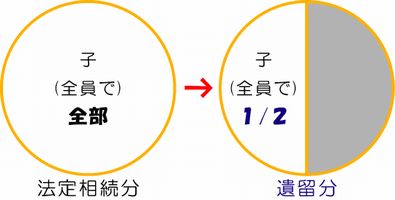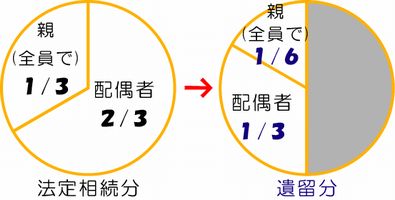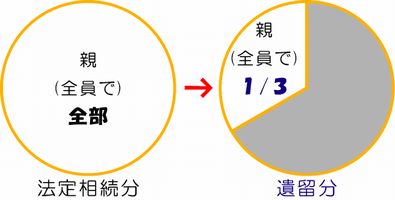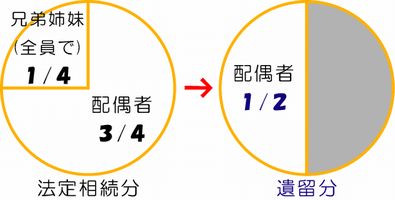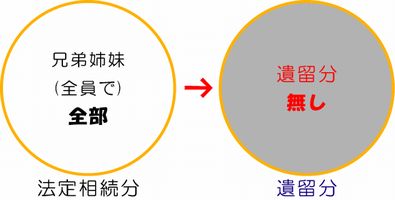���̃y�[�W�ł́A
���̃y�[�W�ł́A
�⌾���ɂ��Đ������܂��B
�������A�⌾���쐬��
�����k�A���˗������\��̕��́A
�ǂ܂Ȃ��Ă����v�ł��B
�����k���ɁA������Ղ��A���J��
�������������܂��̂ŁA
���̂܂����₢���킹�ւ������݉������B
���⌾���Ƃ́E�E�E
���⌾���̎��
���⌾���̕��ʕ���
�@�`���M�؏��⌾�i���Ђ��傤���傢����j
�@�`�閧�؏��⌾�i�Ђ݂��傤���傢����j
�@�`�����؏��⌾�i�����������傤���傢����j
���⌾���̌���
�@�`�②�i�������j
�@�`�������̎w��
�@�`��Y�����̕��@�̎w��
���⌾���s��
���⌾���쐬�Œ��ӂ��ׂ������i�������lj��j
�@�`���葊���l�i�����Ă����������ɂ�j
�@�`�◯���i����イ�Ԃ�j
�@�`�◯�����E�����i����イ�Ԃ��������イ�j
�@�`�������②���n�b�L��������
�@�`�⌾�����쐬
�@�`�⌾�̎����

�ȒP�ɐ�������ƁA��������A�����̍��Y���ǂ��������������ʂɂ������̂��⌾���Ƃ����܂��B
�������A�⌾���́A�@���Œ�߂�ꂽ���@�ȊO�ō쐬���Ă������ł��B
�܂��A�F�m�ǁA�m�I��Q�A���_��Q�i�ȉ��F�m�Ǔ��j�ɂ��A�ӎv�\�͂������Ă���l�́A�⌾�����쐬�ł��܂����B
�⌾�����P�T�������쐬�ł��܂��B
��O�̏ꏊ�ɖ߂�
���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�⌾���ɂ͖@���Œ�߂�ꂽ�A���ʕ����ƌĂ����@���R������܂��B
�܂��A���ʕ����ƌĂ����@���S������܂����A����͐G��܂���B
�i������lj����邱�Ƃ����邩������܂���E�E�E�j
��O�̏ꏊ�ɖ߂�
���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�⌾���̕��ʕ����̂��ꂼ��̕��@�ƃ����b�g�A�f�����b�g�̐����ł��B

|
���M�؏��⌾�i���Ђ��傤���傢����j
|
���M�؏��⌾�́A���̖��̒ʂ�A�⌾���̑S���A���t�A�����̑S�Ă��⌾�Җ{�l�����M�ŏ����A������@�ł��B
��ӂ͔F��ł��ǂ��Ƃ���Ă܂����A�U������h�~����ׂɎ���̕����ǂ��ł��傤�B
�����ɓ���ĕ��邱�Ƃ������ł͂���܂������A�ϑ��h�~�ׂ̈ɕ��������ǂ��ł��傤�B
�������ꂽ�⌾���́A���F�葱�̍ۂɁA�ƒ�ٔ����ő����l���̗���̏�A�J�����Ȃ���Ȃ�܂���B
�����b�g�c
�ȒP�A��y�A��p��������Ȃ��B
�閧�ō쐬�ł���B
�f�����b�g�c
�S�Ď��M�Ȃ̂ő�ρB
���̖@�m�����Ȃ��Ɩ����ɂȂ邨�����A�����l���m�̕����̌����ɂȂ邨���ꂪ����B
�����A�U����ϑ��A�B���̂����ꂪ����B
���F�葱���K�v�ȈׁA���S�シ���ɑ����葱���ł��Ȃ��B
�i�����F�葱�ɂ��Ă��������ŏڂ����������܂��B�j
|
���������֎��M�؏��⌾�쐬�˗������ꂽ�ꍇ�̃����b�g
|
���������Ɏ��M�؏��⌾�쐬�����˗������������ꍇ�A�����A�܂��͕����̌����ɂȂ�Ȃ��悤�����������܂��B
�⌾�����č쐬�����������܂��B
�����{�͎��M�ł��B
�⌾�����{�͑��ɂŕۊǂ������܂��̂ŁA�����A�U����ϑ��A�B���̂����������܂���B
�܂��A�s�����m�̎��`���ɂ��A�閧�͎���܂��B
|
��O�̏ꏊ�ɖ߂�
���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

|
�閧�؏��⌾�i�Ђ݂��傤���傢����j
|
�閧�؏��⌾�́A�⌾���{���͎��M�ł���K�v�͂���܂���B
�p�\�R����[�v���ł̍쐬���M�ł��\���܂���B���t���s�v�ł��B
�������A�⌾�Җ{�l�̏����Ɖ���͕K�v�ł��B
��ӂ͔F��ł��ǂ��Ƃ���Ă܂����A�^�����𑝂��Ӗ��ł�����̕���
�ǂ��Ǝv���܂��B
���������{�����ɓ���A�{���Ŏg�p������ƕK��������ŕ��܂��B
�i�����̕����ƕ�����K���⌾�Җ{�l�����Ȃ��Ƃ����܂���B�j
���ɁA�⌾���{�����������ؐl�Q�l�ƈꏏ�Ɍ��ؖ���ɍs���܂��B
�i���ؐl�ɂȂ�ɂ����̏���������܂��B�ڂ������������j
���ؖ���Ō��ؐl�Ɏ����̈⌾���ł��邱�Ƃ�`���A���̂��Ƃ����ؐl�������ɋL�ڂ��A���t�����܂��B
�Ō�Ɉ⌾�ҁA�ؐl�Q�l�A���ؐl�������ɏ������Ċ����ł��B
�閧�؏��⌾�̌��{�͈⌾�Җ{�l���ۊǂ��܂��B
���ؖ���ւ̎萔����11,000�~�ł��B
�����b�g�c
�p�\�R����[�v���ł̍쐬�n�j�A��M�쐬���n�j�B
���S�ɔ閧�ɂł���B
�閧�؏��⌾���쐬�����L�^�����ؖ���Ɏc��B
�i���쐬�������������ň⌾���e�͎c��Ȃ��j
�f�����b�g�c
���̖@�m�����Ȃ��Ɩ����ɂȂ邨�����A�����l���m�̕����̌����ɂȂ邨���ꂪ����B
�����A�B���̂����ꂪ����B
���Q�W�̖����ؐl���Q�l�K�v�B
�i���ؐl�ɂ��Ă��������j
�����Ɍ��ؖ���ɏo�����K�v������B
���ؖ���ւ̎萔���P�P�C�O�O�O�~���K�v�B
���F�葱���K�v�ȈׁA���S�シ���ɑ����葱���ł��Ȃ��B
�i�����F�葱�ɂ��Ă��������ŏڂ����������܂��B�j
|
���������֔閧�؏��⌾�쐬�˗������ꂽ�ꍇ�̃����b�g
|
���������ɔ閧�؏��⌾�쐬�����˗������������ꍇ�A�����A�܂��͕����̌����ɂȂ�Ȃ��悤�����������܂��B
�⌾�����č쐬�Ƒ�M�A�ؐl�Q�l�����������܂��B
�⌾�����{�͑��ɂŕۊǂ������܂��̂ŁA�����A�B���̂�����͂���܂���B
�܂��A�s�����m�̎��`���ɂ��A�閧�͎���܂��B
|
��O�̏ꏊ�ɖ߂�
���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

|
�����؏��⌾�i�����������傤���傢����j
|
�����؏��⌾�́A���ؐl���쐬�����⌾���̂��Ƃł��B
���ؐl���쐬����̂ŁA�������Ƃ��ċ������͂�����A���S���m���ł��B
����ɁA���̊m�������瑼�̈⌾���ɂ͕K�v�����F�葱���s�v�ł��B
�ʏ�A�����؏��⌾���쐬����ꍇ�A���炩���ߌ��ؖ���ɍs���A�⌾���e��K�v���ށA�����؏��⌾�쐬�����̑ō��������܂��B
�⌾���e�����܂�A�K�v���ނ���������A�쐬�����ɏؐl�Q�l�ƈꏏ�Ɍ��ؖ���֍s���܂��B�i���ؐl�ɂ��Ă��������j
���ؖ���Ō��ؐl�Ɉ⌾���e��`���A��������ؐl���M�L���܂��B
�M�L���I���ƁA���ؐl���⌾�Җ{�l�Əؐl�Q�l�ɓ��e�̊m�F�����A�⌾�҂Əؐl�Q�l�A���ؐl�������E���Ċ����ł��B
�Ȃ��A�����؏��⌾�̏ꍇ�A�⌾�҂̉�����K�������ł��B
�⌾�����{�͌��ؖ���ɕۊǂ���A������B���̂����ꂪ����܂���B
���ؖ���ւ̎萔���͈ȉ��̒ʂ�ł��B
�i�ړI�̉��z�j |
�i�萔���j |
| �P�O�O���~�ȉ� |
�T�O�O�O�~ |
| �P�O�O���~���Q�O�O���~�ȉ� |
�V�O�O�O�~ |
| �Q�O�O���~���T�O�O���~�ȉ� |
�P�P�O�O�O�~ |
| �T�O�O���~���P�O�O�O���~�ȉ� |
�P�V�O�O�O�~ |
| �P�O�O�O���~���R�O�O�O���~�ȉ� |
�Q�R�O�O�O�~ |
| �R�O�O�O���~���T�O�O�O���~�ȉ� |
�Q�X�O�O�O�~ |
| �T�O�O�O���~���P���~�ȉ� |
�S�R�O�O�O�~ |
| �P���~���R���~�ȉ� |
�S���R�O�O�O�~�ɂT�O�O�O���~�܂ł��Ƃ�
�P���R�O�O�O�~�����Z |
| �R���~���P�O���~�ȉ� |
�X���T�O�O�O�~�ɂT�O�O�O���~�܂ł��Ƃ�
�P���P�O�O�O�~�����Z |
| �P�O���~����ꍇ |
�Q�S���X�O�O�O�~�ɂT�O�O�O���~�܂ł��Ƃ�
�W�O�O�O�~�����Z |
�y�@���s�ׂɌW��؏��쐬�̎萔���z
�����b�g�c
���F�葱���s�v�Ȃ̂ŁA���S�シ���ɑ����葱���ł���B
�⌾�����{�͌��ؖ���ɕۊǂ����̂ŁA�����A�U����ϑ��A�B���̂����ꂪ�Ȃ��B
�����ɂȂ�\�����Ⴂ�B
�f�����b�g�c
���Q�W�̖����ؐl���Q�l�K�v�B
�i���ؐl�ɂ��Ă��������j
�ō����ׂ̈ɕ����ɐ���A���ؖ���ɏo�����K�v������B
��ӏؖ�����ːГ��{���A����ނ̏��ނ��K�v�B�i�⌾���e�ɂ��j
���ؖ���ւ̎萔�����K�v�B�i�⌾���e�ɂ���ĕϓ��j
|
�������������؏��⌾�쐬�˗������ꂽ�ꍇ�̃����b�g
|
���������Ɍ����؏��⌾�쐬�����˗������������ꍇ�A���ؖ���Ƃ̑ō�����K�v���ނ̎��W�A�⌾�����č쐬�A�ؐl�Q�l�ȂǁA�S�Ă��������܂��B
�⌾���̐��{�A���{�͑��ɂŕۊǂ������܂��B
�܂��A�s�����m�̎��`���ɂ��A�閧�͎���܂��B
|
��O�̏ꏊ�ɖ߂�
���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�⌾���̌��F�葱�́A�S���Ȃ����⌾�҂̏Z�����NJ�����ƒ�ٔ����ɁA�⌾���̕ۊǎҁA�������͔����҂��������l���⌾�������F�\�������܂��B
�\���Ăɂ́A�⌾�҂̏o�����玀�S�܂ł̑S�Ă̌ːГ��{�A���Г��{�A�������ːГ��{�ƁA�����l�S���̌ːГ��{�����K�v�ł��B
�\���Ă�����ƁA�ƒ�ٔ�������\���l�Ƒ����l�S���Ɍ��F����X���Œm�点�Ă��܂��B
���F���ɉƒ�ٔ����ő����l�S���̗���̂��ƁA�⌾�����J������܂��B
�����Q���ł��Ȃ������l�����Ă��A���F�葱�͍s���܂��B
���F�葱�́A���F�����_�ł̈⌾���̌`����ԁA�⌾���e�m�ɂ��āA�⌾���̋U���A�ϑ���h�~����ׂ̎葱�Ȃ̂ŁA�⌾�����L�����������f����킯�ł͂���܂���B
�Ȃ��A���ꂽ�⌾�������F�葱�����ɊJ�������ꍇ�A�ٔ��������T���~�ȉ��̉ߗ��i�����̂悤�Ȃ��́j�ɏ������܂��B
�������A�⌾���������؏��⌾�̏ꍇ�A���F�葱���s�v�ł��B
��O�̏ꏊ�ɖ߂�
���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�閧�؏��⌾�������؏��⌾���쐬����ꍇ�A�Q�l���ؐl���K�v�ł��B
����́A�⌾�Җ{�l�ł��邱�ƁA�⌾�Ҏ��g�̈ӎv�ɂ����́A���ؖ���ň⌾�����쐬�������ƂȂǂ��m�F����ׂł��B
�܂��A�ȉ��̐l�͏ؐl�ɂȂ�܂���B
�@�����N��
�A�⌾�҂̑����l��A���^����l
�B�A�̔z��҂Ⓖ�n����
�C���ؐl�̔z��҂�A�S�e�����̐e��
�D���ؐl�̏��L��g�p�l
���܂�A�ؐl�́A�⌾�҂̑����Ƃ��S���W�̖����l�����Ȃ�܂���B
�����������Ɉ⌾���쐬���˗����ꂽ�ꍇ�A�ؐl�Q�l�Ƃ����������܂��B
��O�̏ꏊ�ɖ߂�
���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�@�I�ɗL���ȁA������Ƃ����⌾�����c���Ă����A�⌾�҂̎���A�����Ƃ����⌾���̓��e�̂ǂ���Ɍ��͂��������܂��B
�⌾���őS�Ă̍��Y�ɂ��Ė��L���Ă����A��Y�������c�������K�v�͂���܂����B
�Ȃ̂ŁA�����l�S�������ӂ������Ă������葱���ł��܂��B
�i����Y�������c�ɂ��Ă��������j
��Y�������c�����Ȃ��̂ŁA��Y�������c�����s�v�ł��B
�i����Y�������c���ɂ��Ă��������j
�܂��A�@�葊���l�ȊO�̐l�ɂ���Y��^���邱�Ɓi�②�j���ł��܂��B
�i���@�葊���l�ɂ��Ă��������j
�����āA�@�葊�����Ƃ��Ⴄ�����ł̈�Y�����i�������̎w���j���ł��܂��B
�i���@�葊�����ɂ��Ă��������j
�������A���̑����l�ɂ́A�@���ŕۏ���Ă���Œ���̊����i�◯���j������̂ŁA���ӂ��K�v�ł��B
����ɁA����̍��Y�����̐l�ɑ����������i��Y�����̕��@�̎w���j���ł��܂��B
��O�̏ꏊ�ɖ߂�
���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�@�葊���l�ȊO�ɍ��Y��^�������ꍇ�A�⌾�����K�v�s���ł��B
�i���@�葊���l�ɂ��Ă��������j
�⌾���Ŗ@�葊���l�ȊO�̐l�ɍ��Y��^���邱�ƁA�܂�⌾�ɂ�鑡�^�̂��Ƃ��②�i�������j�Ƃ����܂��B
�����l�ȊO�ւ̈②�Ƃ́A�q�������l�̏ꍇ�̑��܂��͐e��Z��o���A�����l�̔z��ҁi��F��삵�Ă��ꂽ���j�̉łȂǁj������W�ҁA�܂��͂����b�ɂȂ������l�Ȃǂɑ��Ă̈②�ł��B
�܂��A�⌾�҂͈②������ꍇ�A�②�ɏ��������邱�Ƃ��ł��܂��B
�����Ƃ́A�w���Y�����������ɁA�y�b�g�̖ʓ|�����邱�Ɓx�Ȃǂł��B
�②����l�̂��Ƃ������i���ア����j�ƌĂт܂����A�②���邩�Ȃ��������҂̎��R�ł��B
�܂��A�⌾���œ���̒c�̂ւ���t���ł��܂��B
��O�̏ꏊ�ɖ߂�
���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�⌾���ŁA�@�葊�����Ƃ͈Ⴄ�����ő��������邱�Ƃ��ł��܂��B
�i���@�葊�����ɂ��Ă��������j
������������̎w���Ƃ����܂��B
�Ⴆ�A��J���������������A�g�̂̎ア���q����ɁA���̑����l��葽�����Y���c���Ă��������ꍇ�ȂǂɁA�⌾���ő������̎w������Ă����܂��B
�������A���̑����l�ɂ́A�@���ŕۏ���Ă���Œ���̊����i�◯���j������̂ŁA���ӂ��K�v�ł��B
��O�̏ꏊ�ɖ߂�
���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�⌾���ł́A�N�ɉ��𑊑�������̂����w��ł��܂��B
�������Y�����̕��@�̎w���Ƃ����܂��B
�_�Ƃ�l��Ƃ��c��ł��鎩�c�Ǝ҂̏ꍇ�A��Y�����̕��@���w�肵�A��p�҂��W���Y�𑊑��ł���悤�ɂ��Ă����Ȃ��ƁA���Y�����U���Čo�c�����藧���Ȃ��Ȃ邨���ꂪ����܂��B
�������A��l�̑����l�ɍ��Y���W�����A�◯����N�Q���Ă��܂������ȏꍇ�́A���̑����l�ւ̔z�����K�v�ł��B
�܂��A�⌾������Y�����������ԋ֎~�i�T�N�ȓ��j���邱�Ƃ��ł��܂��B
��O�̏ꏊ�ɖ߂�
���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

���������⌾�����c���Ă��A�⌾���e����������Ȃ���ΈӖ�������܂���B
�����l�S�������͂������Ď����ł���Ηǂ��̂ł����A�⌾���e�ɕs�������鑊���l������ꍇ�Ȃǂɂ́A�����������������܂���B
�X���[�Y�Ɉ⌾���e����������ׂɂ��⌾�����⌾���s�҂̎w�������Ă����܂��傤�B
�⌾���s���i��������������j�Ƃ́A�⌾���̓��e����������l�̂��Ƃł��B
�⌾���s�҂́A�����N�҂�j�Y�҂łȂ���ΒN���w�肵�Ă��\���܂��A�����葱�ɂ͖ʓ|�Ȃ��̂������A�K�v�ȏ��ނ���������̂ŁA�����l���m�����͂�������ꍇ�ł��A�@���ɏڂ������Ƃ��w�肵���������S�ł��B
�����l���m�ň⌾���e���������邱�Ƃ�����A�⌾���s�҂��K�v�ȏꍇ�Ɉ⌾�ň⌾���s�҂��w�肳��Ă��Ȃ��A�܂��͎w�肳��Ă����⌾���s�҂������J�n�̎��i�⌾�҂̎��S���j�Ɋ��Ɏ��S���Ă����ꍇ�ɂ́A���Q�W�ҁi�����l����҂Ȃǁj�����������ƒ�ٔ����Ɉ⌾���s�҂�I�C���Ă��炢�܂��B
��O�̏ꏊ�ɖ߂�
���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�⌾���쐬�̍ۂ̒��ӓ_�ł��B�����lj����Ă����܂��B

|
���葊���l�i�����Ă����������ɂ�j
|
�⌾���쐬���_�ŁA�@�葊���l�ɂȂ�\��̐l�̂��Ƃ��A���葊���l�i�����Ă����������ɂ�j�Ƃ����܂��B
�i���@�葊���l�ɂ��Ă��������j
�⌾�����쐬����ۂɁA���葊���l�ɔz��҂�q�A�e�����܂܂��ꍇ�ɁA���葊���l�ɘR�ꂪ����ƁA�◯���̖�����⌾���ǂ���ɂȂ�Ȃ�������������܂��B
�i���◯���ɂ��Ă��������j
�⌾�����쐬����ꍇ�A���葊���l�ɘR�ꂪ�Ȃ��悤�\�����ӂ��Ă��������B
�������A�����܂ł��⌾���쐬�̎��_�ő������J�n���ꂽ�ꍇ�ɑ����l�ɂȂ邾�낤�Ɛ��肳��邾���ŁA���ۂ̂Ƃ���A�⌾�҂��S���Ȃ��đ������J�n�����܂ł́A�N�������l�ɂȂ�̂�������܂���B
���ہA�����J�n�̎��ɂ́A�⌾���ɋL�ڂ������葊���l�����ɖS���Ȃ��Ă����\��������܂��B
�Ⴆ�A�⌾���̖����@�葊���̏ꍇ�A�����l�̒��j�����ɖS���Ȃ��Ă��Ă��A���j�Ɏq������A���̎q������ɑ����i��P�����j���܂����A���ꂪ�A���j������̍��Y�𑊑�������⌾�����Ă���ꍇ�A�����J�n�������j�����ɖS���Ȃ��Ă����ƁA���j�̎q������ɁA���̓���̍��Y�𑊑������킯�ł͂���܂����B
�i���@�葊�����������A�q�̑�P�������������j
����́A�����l�ł͂Ȃ��l�ɓ���̍��Y���②����ꍇ�����l�ŁA�����J�n���ɁA�⌾���Ŏw�肵�����҂����ɖS���Ȃ��Ă����ꍇ�A�②�̌��͂��������܂����̂ŁA���҂ɑ����āA���҂̑����l�Ɉ②������킯�ł͂���܂����B
���̂悤�ɁA�⌾��������̍��Y���A����̑����l��A���҂ɗ^�������ꍇ�́A�w�肵�������l����҂��������ł��Ȃ��ꍇ�ɔ������⌾�����쐬���܂��傤�B
�i���w�����������ł��Ȃ��ꍇ�́����ɑ���������x�Ȃǁj
��O�̏ꏊ�ɖ߂�
���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�@�葊���l�ɂ́A�@���ōŒ���ۏ���Ă��鑊����������܂��B
������◯���i����イ�Ԃ�j�Ƃ����܂��B
�⌾�����쐬����ꍇ�A�◯���ɒ��ӂ��Ȃ����⌾���ǂ���ɂȂ�Ȃ������ꂪ����܂��B�i���◯�����E�����j
�@�葊���l���z��҂Ǝq�i���j�̏ꍇ�A�e�����l�̈◯���́A�@�葊�������P/�Q�Ȃ̂ŁA�z����P/�S �F �q�i�S���Łj�P/�S�ɂȂ�܂��B

�@�葊���l���z��҂݂̂̏ꍇ���◯���́A�@�葊�������P/�Q�Ȃ̂ŁA�z����P/�Q�ɂȂ�܂��B
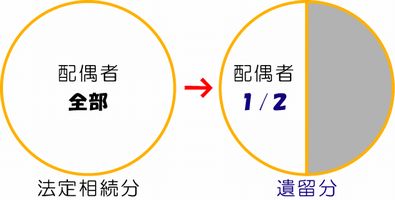
�@�葊���l���q�i���j�݂̂̏ꍇ���◯���́A�@�葊�������P/�Q�Ȃ̂ŁA�q�i�S���Łj�P/�Q�ɂȂ�܂��B
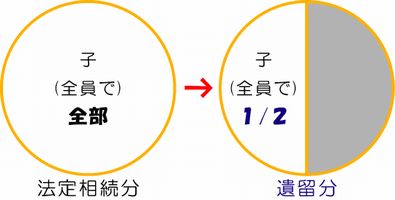
�@�葊���l���z��҂Ɛe�i�c����j�̏ꍇ���e�����l�̈◯���́A�@�葊�������P/�Q�Ȃ̂ŁA�z����P/�R �F �e�i�S���Łj�P/�U�ɂȂ�܂��B
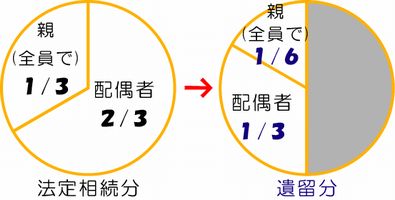
�������A�@�葊���l���e�i�c����j�݂̂̏ꍇ�̈◯���́A�@�葊�������P/�R�ł��B
�ł�����A�e�i�S���Łj�P/�R�ɂȂ�܂��B
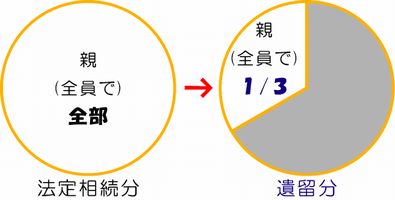
�@�葊���l���z��҂ƌZ��o���i���Áj�̏ꍇ�̈◯���́A�z��҂͖@�葊�������P/�Q�A�Z��o���Ɉ◯���͂���܂����B
�Ȃ̂ŁA�z����P/�Q �F �Z��o���i���Áj�◯�������ł��B
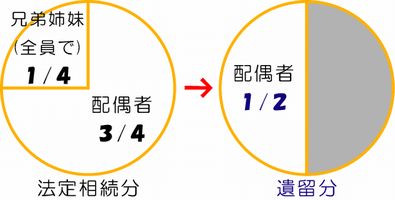
�@�葊���l���Z��o���i���Áj�݂̂̏ꍇ�A�Z��o�����◯���͂���܂����B
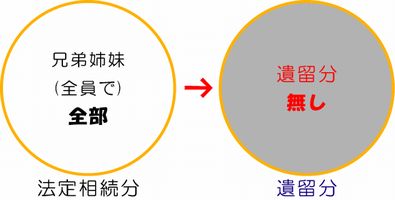
�◯���́A�@���ŕۏ�����Ă���̂ŁA�⌾���ɂ���āA�◯���������Ȃ������ł��������ł��Ȃ����������l�́A�◯����N�Q���Ă���l�i���@�葊������葽���������������l����҂Ȃǁj�ɑ��āA�◯���͈͓̔��ŁA�������Y���Ԃ��悤�ɐ����ł��܂��B
������A�◯�����E�����i����イ�Ԃ��������イ�j�Ƃ����܂��B
��O�̏ꏊ�ɖ߂�
���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

|
�◯�����E�����i����イ�Ԃ��������イ�j
|
�⌾���ɂ��A�����������Y���◯���ɖ����Ȃ������l�́A�����̈◯����N�Q���Ă��鑊���l����҂ɑ��A�◯���͈͓̔��ő������Y�����߂��◯�����E�������ł��܂��B
�◯�����E�����́A�◯����N�Q���Ă���l�ɑ��Ĉӎv�\�����邾���ŗǂ��Ƃ���A�ٔ����Ȃǂ�ʂ��K�v�͂���܂���B
�������A�◯�����E�����́A�����J�n�i�푊���l�̎��S���j����сA�◯�����N�Q����Ă��邱�Ƃ�m���Ă����P�N�ȓ������ł��܂���B
�܂��A�m��Ȃ��ꍇ�ł��A�����J�n�i�푊���l�̎��S���j�����P�O�N���߂���Ƃł��Ȃ��Ȃ�܂��B
���̈◯�����E�����́A�◯���������Z��o���͂��邱�Ƃ��ł��܂����B
�z��҂�q�i���j�A�e�i�c����j�����葊���l�̏ꍇ�́A�◯���ɔz�����A�◯�����E����������Ȃ����e�̈⌾�����쐬���܂��傤�B
��O�̏ꏊ�ɖ߂�
���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

|
�������Ȃ̂��②�Ȃ̂��n�b�L��������
|
�����l�ɑ��ẮA�������Ȃ̂��A�②�Ȃ̂��n�b�L�������邽�߂ɂ��A�w�`��^����x�ł͂Ȃ��A�w�����������x�ƕ\�����������ǂ��B
�o�L�葱�̍ۂɁA�����̏ꍇ�́A��������҂��P�ƂŐ\���ł��܂����A�②�̏ꍇ�́A�����������l�S�����͈⌾���s�����A�ꏏ�ɐ\�����Ȃ�������܂����B
��O�̏ꏊ�ɖ߂�
���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�⌾�����쐬���A���e���������Ă���ꍇ�A���t���V���������L���ɂȂ�܂��B
����́A�V�����⌾�����Â��⌾���̓��e���ύX�܂��͎���������ƂɂȂ�����ł��B
�����̈⌾���ŁA���e�S�Ă��������Ă���A�V�������̈⌾�����L���ŁA�Â����̈⌾���͖����ɂȂ�܂��B
�������A�ꕔ���݂̖̂����ł���A�V�����⌾���ł��̕������ύX���ꂽ�Ƃ��������ŁA����ȊO�͌Â��⌾�����L���̂܂��ł��B
�܂��A�Â��⌾�����L�ڂ̖����������V�����⌾���ɋL��������A�⌾���e�̒lj��Ƃ������ƂŁA�ǂ���̈⌾�����L�ڎ����͑S�ėL���ł��B
��O�̏ꏊ�ɖ߂�
���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�

�⌾����������@���R������܂��B
�@�⌾�Җ{�l�������̈ӎv�ň⌾����j������
�⌾�Җ{�l���⌾����j������R�₷�ȂǁA���炩�̕��@���j�����邱�Ƃň⌾������������ƂɂȂ�܂��B
�A�V�����⌾���Ŏ����
�O�̈⌾���ƑS������������e�̐V�����⌾�����������A�V�����⌾�����u���̈⌾�����ȑO�̈⌾���͑S�Ď�����v�ƋL������Ȃǂ��āA�O��̈⌾����������Ƃ��ł��܂��B
�B�⌾���ɋL�ڂ������Y����������
�⌾�����L�ڂ������Y�����肠����������Ȃǂ��āA�������邱�Ƃł��̈⌾������������̂Ƃ݂Ȃ���܂��B
�A��B�ł̎�����́A���e�S�Ă��������Ă���A�L�ڍ��Y�S�������������ꍇ�́A�⌾�S��������������ƂɂȂ�܂����A�ꕔ�̖����⏈���̏ꍇ���̕����ȊO�̈⌾�͎���������Ƃɂ͂Ȃ�܂����B
�܂��A�O�̈⌾��������⌾��s�ׂ�������Ă��A��x������ꂽ�⌾�̌��͉͂��܂����B
��O�̏ꏊ�ɖ߂�
���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�
�������ň⌾�����쐬�������ꍇ�ł��A���ꂪ�������邾���̃A�h�o�C�X������������܂��̂ŁA�܂��͂����k���������I
���⌾���ɂ��Ă̂��₢���킹���������܂ŁI
��O�̏ꏊ�ɖ߂�
���̃y�[�W�̃g�b�v�ɖ߂�
|
 ���̃y�[�W�ł́A
���̃y�[�W�ł́A